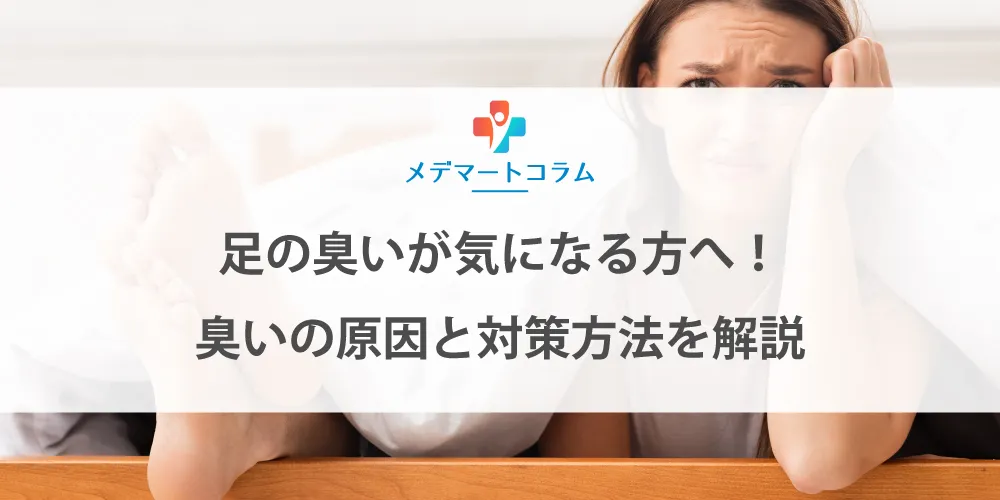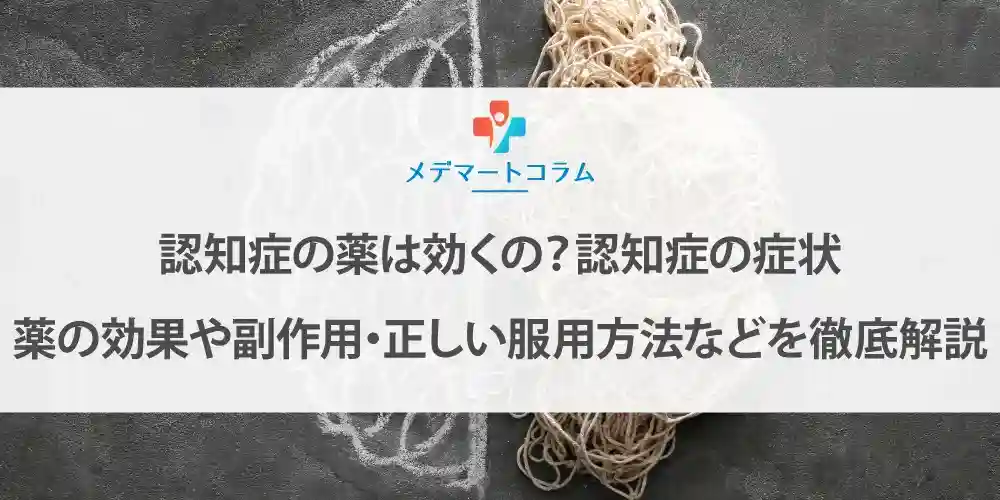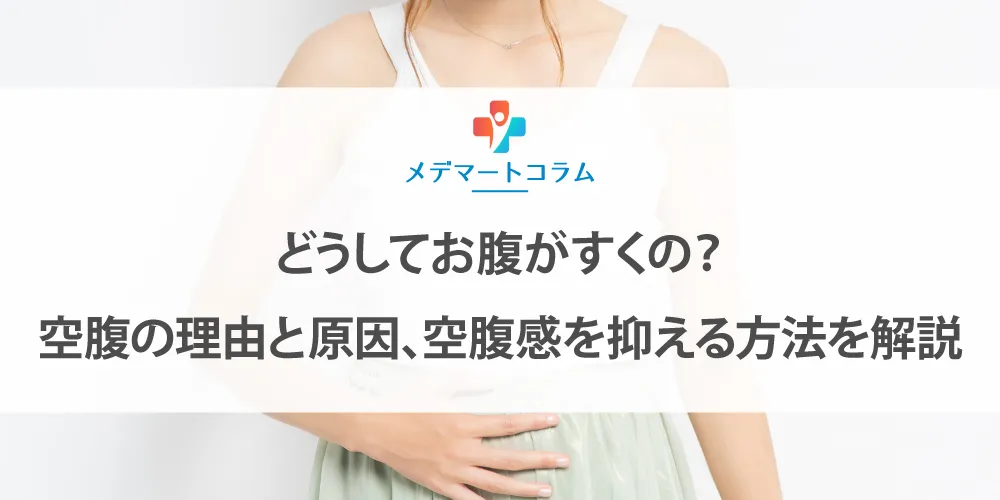足の臭いの原因は雑菌の繁殖
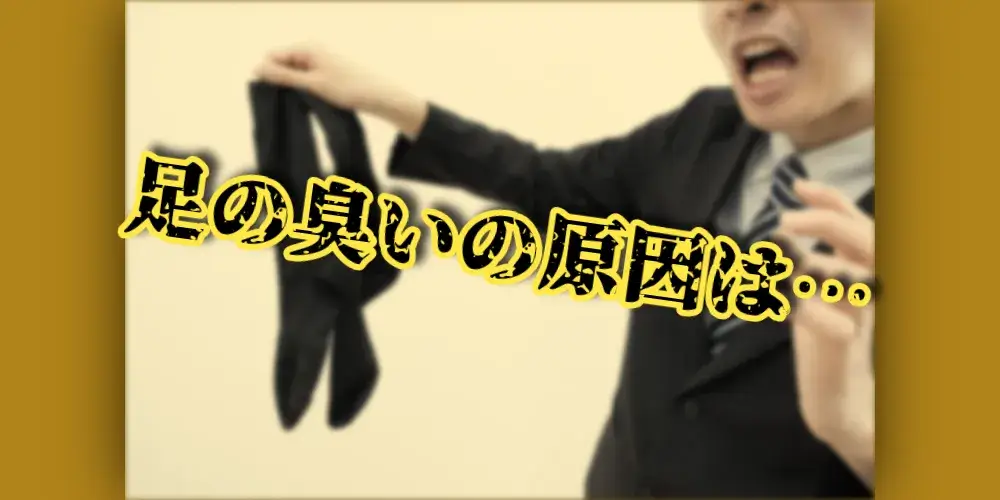
足の臭いの主な原因は、足の皮膚に常在する雑菌の繁殖にあります。
足には多数の汗腺(かんせん)、とくにエクリン腺が存在します。これは人の身体のなかでも、胸や背中の5~10倍もあり、足は汗をかきやすい場所なのです。
そんな足裏では、通常1日にコップ1杯分もの汗を排出します。
この汗が雑菌のエサとなり、靴の中の高温多湿な環境で雑菌が異常繁殖します。
雑菌が汗や古い角質、皮脂などを分解することで、「イソ吉草酸」「イソ吉草酸アルデヒド」「酢酸」などの強い臭いのある物質が生成されます。特に「イソ吉草酸」は法律で規制されるほどの強い悪臭です。
足は汗を拭き取りにくく、靴や靴下で覆われているため蒸れやすく、雑菌の温床となります。
では、臭いの原因となる雑菌ですがいつ繁殖しているのでしょうか。
足裏には多くの雑菌が存在していますが、特に次のような時に繁殖しやすくなります。
足裏の雑菌が繁殖しやすい状況
- 普段の生活をしている中で足裏に汗をかいて蒸れたとき
足は普段、靴下や靴を履いているため、汗をかくと蒸れて乾きにくくなります。高温多湿な環境は雑菌の繁殖を促すため、蒸れは臭いの原因となります。 - 雑菌の温床となる皮脂や垢が増えてきたとき
爪や指の間、かかとなど汚れが溜まりやすい箇所では、皮脂や垢が雑菌のエサとなり繁殖が進みます。 - 角質の層が厚くなったとき
足の角質層は厚いため剥がれやすく、雑菌が分解することで臭いの原因となります。
足が臭う人の特徴

足が臭くなりがちな人に共通する特徴として、以下の4つがあげられます。
①足に汗をかきやすい体質
足に汗をかきやすい体質の人は、足が蒸れて湿った環境になりやすく、そこで雑菌が繁殖して臭いの原因になります。
なかでも気温ではなくストレスや緊張などが引き金となり発汗する「精神的発汗」は足の裏や手のひらなど限られた部位でしか発汗しません。
脇の下と同じく、足の汗腺は発汗量は個人差が大きい部位です。体質的に汗をかきやすい人は、足の汗で足が蒸れてしまいがちです。
②靴や靴下を長時間履く
靴や靴下の中は閉鎖的な環境で、湿気がこもりやすくなっています。
そのため長時間靴や靴下を履き続けると、足の湿気と熱で菌が繁殖しやすくなり、臭いの原因となります。
特に通気性の悪い革の靴やブーツ、パンプス、また厚手の靴下やタイツ、ストッキングなどは要注意です。
③同じ靴を連日履く
同じ靴を繰り返し履くと、靴の中に雑菌が蓄積していきます。異なる靴を交替で履くより、同じ靴を履き続けるほうが、臭いが生じるリスクが高くなります。
誰でもお気に入りの靴があれば毎日履きたいものですが、そればかり履き続けてしまうことは逆に足の臭いが強くなる原因となります。
④足に汚れがたまりやすい体質
体質的に足の皮脂や垢が多い人
このタイプの人は、足を洗ってもすぐに汚れがたまってしまいます。
足の皮脂や垢が多く分泌されるため、普段から丁寧に足を洗い、清潔に保つことが重要です。
足の汚れを落とすのが不得意な人
このタイプの人は、洗い方が下手だったり、面倒がって丁寧に洗っていなかったりするために、汚れがたまりやすくなります。
どちらのタイプでも、足のニオイは強くなりやすいので、注意が必要です。
足の臭いは主に汗と閉鎖的な靴の環境が原因です。汗や靴の管理を意識して、蒸れやすい足を快適に保つことが大切です。
嫌な臭いのための対策と予防策

足の臭いは主に汗と靴の中の菌が原因で発生します。臭いを防ぐには次の8つのような対策が効果的です。
①汗をかきやすい体質の人は、足用の制汗剤を使う
汗で足が蒸れてしまう体質の人は、足用の制汗剤を使うことをおすすめします。制汗剤を塗布することで、足の発汗を抑え、高温多湿な環境を作らずに済みます。
クリームタイプの制汗剤なら、足の裏や爪の間など細かい部分にもしっかり浸透し、効果的です。
お風呂上がりなど清潔なタイミングで、足の裏全体に塗り込んでください。
②通気性の良い素材の靴下と靴を選ぶ
靴下は、メッシュ生地や抗菌機能のあるものを選ぶと良いでしょう。綿100%のような通気性の高い素材がおすすめです。
また、5本指タイプの靴下は、指の間の汗を吸収しやすくおすすめです。靴は、合成素材よりも天然素材のものの方が通気性が高く、蒸れにくくなります。
③同じ靴を連日履かない
同じ靴を毎日履き続けると、靴の中に汗や皮脂、雑菌が蓄積していきます。
少なくとも3足以上の靴を用意して、毎日履き替えるようにしましょう。1足につき1日空けて履く、といったサイクルが理想的です。
④消臭スプレーや脱臭剤で靴内を定期的にケアする
靴内に付着した汗や皮脂、雑菌を除去するため、スプレータイプや脱臭剤の消臭グッズを利用しましょう。
使用頻度が高い靴は1日1回、それ以外は数日に1回のペースでケアします。効果の高い商品を選び、使い方を守って使用しましょう。
⑤こまめに足を洗い、爪を短く切る
少なくとも1日1回、足を石鹸でしっかり洗浄しましょう。
特に爪の間や指の間は汚れが溜まりやすいので、重点的に洗います。爪は短く切って清潔な状態を保ち、汚れの温床にしないようにします。
⑥足用石けんで洗浄し、古い角質をケアする
足用の石けんや薬用石けんを使って洗うことで、垢や汗、雑菌をしっかり洗い流せます。
また、ピーリングケアなどで古い角質を除去することも大切です。
⑦素足でいる時間を設け、通気性を高める
居宅内ではできるだけ素足にしましょう。靴下や靴を履かないようにすることで、足の通気性が高まり、汗や湿気がためにくくなります。
清潔な足を保ちつつ、蒸れにくい環境を作ることが大切です。
⑧重曹による足の臭い対策
重曹は、除菌や消臭、洗浄力が高いことで知られています。足の臭い対策としても効果的なので、活用方法を覚えておくと便利です。
重曹の具体的な使い方は以下の通りです。
重曹入りの足湯を作る
洗面器にぬるま湯を用意し重曹を大匙1~2杯程度入れ混ぜる。足を入れ浸かることで汚れを洗い流す。
重曹には、酸性の汚れを中和するアルカリ性と、除菌作用があります。
これらの性質が、臭いの原因である汚れや菌を減らすのに効果的です。重曹の使い方を上手に取り入れ、清潔な足を保ちましょう。
以上のように、汗や汚れ、角質をコントロールし、靴の管理を心がけることが大切です。
靴の中だけでなく、足自体の清潔が臭い予防のカギとなります。
病気が原因で足が臭う?
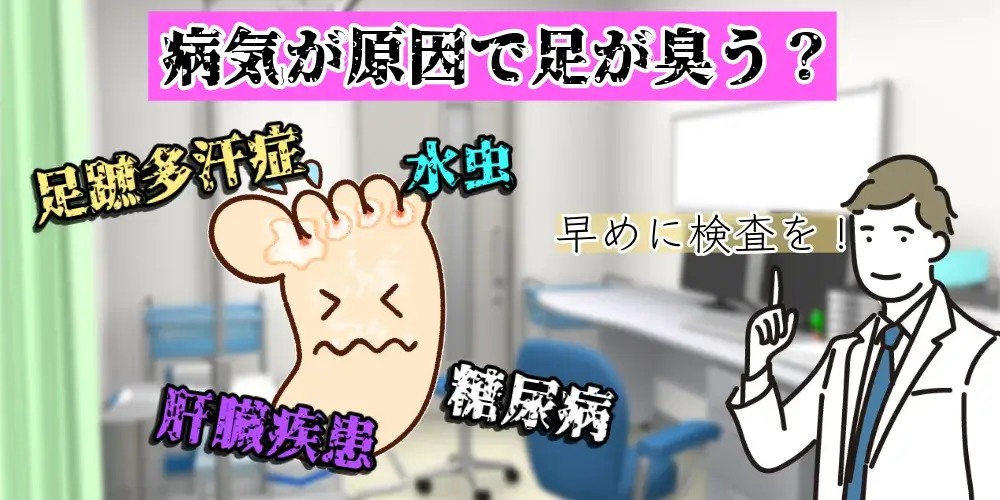
足の臭いはだんだんと強くなるばかりで、排泄物の臭いのようになることがあります。
その場合、何度洗っても臭いが取れないのが特徴です。
このような症状は、次の2つの病気が原因の可能性があります。
水虫
1つ目は、「水虫」です。水虫はカビの一種である白癬菌が繁殖することで起こる疾患です。
湿った環境を好むため、手の指の間や足などが感染しやすくなります。
水虫の症状としては、かゆみ、垢のようなものができる、皮膚がふやけるなどがあります。
特有の臭いを発し、治療しないと周囲の人に移る可能性があるため要注意です。
足蹠多汗症(そくせきたかんしょう)
2つ目は、「足蹠多汗症(そくせきたかんしょう)」です。この病気では、手のひらや足の裏など限られた部位から異常に汗をかきます。
子どもに多く靴下が濡れるほどの多量の汗が特徴で、汗で足が蒸れ、臭いの原因になります。
原因ははっきりしていませんが、精神的ストレスなどが関係していると考えられています。
多汗症については以下のサイトで詳しく解説いたします。
このような病気が原因の場合、足を清潔にしていても臭いは治まりません。できるだけ早く専門医の診断を受けることが大切です。
水虫では薬物治療が行われ、多汗症では内服薬や外用薬などで改善を図ります。
水虫予防のためには、公共の浴場やジムのシャワーを使用後は足をよく乾かすことや、他人とタオルや靴を共有しないことが重要です。また、多汗症の方は、通気性の良い靴や吸汗力の高い靴下を選び、清潔な足を保つようにしましょう。
臭いの程度が強く、湿疹やかゆみもある場合は要注意です。我慢せずに早めに医師の診断を受けることをおすすめします。
病気に対する正しい治療を受けることで、足の臭いも改善される可能性が高くなります。清潔にしていても臭いが取れない場合は、一度専門医に相談しましょう。
他の部分の臭いも気になる場合
また、足や脇の下など部分的なものだけでなく、からだ全体から異臭がする場合、その原因に次のような病気が隠れている可能性があります。
糖尿病
糖尿病では、血糖値が高くなる病気です。エネルギーが不足するため、肝臓でケトン体と呼ばれる物質が作られます。
ケトン体にはフルーツが腐ったような甘酸っぱい臭いがあり、体臭の原因となります。尿量が増えたり、のどの渇きが激しくなるなどの自覚症状がある場合は要注意です。
肝臓疾患
肝臓の病気では、アンモニアなどの老廃物の分解が上手くいかなくなります。
その結果、アンモニアの臭いを含む汗をかくようになるため、ツンとした体臭が生じます。
肝機能低下のサインとして、疲れやすさや食欲不振なども現れます。
このような場合、足だけのケアでは臭いは消えず、病院での治療が必要です。
からだ全体から強い臭いが生じるようなら、糖尿病や肝臓疾患の可能性も考え、早めに専門医の検査を受けることをおすすめします。
病気が原因の場合、治療によって体臭も改善できることがあります。我慢せずに早期発見と治療を心がけましょう。
足の臭いを抑えるためのグッズ

足の臭いを抑えるグッズはたくさん販売されております。中でも厳選した商品をジャンル別に紹介していきます。
制汗・消臭剤
- 8×4フットスプレー(花王)
- デオナチュレ 足指さらさらクリーム(シービック)
- ドクターショール 消臭・抗菌靴スプレー(レキットベンキーザー)
足用洗浄剤
- 重曹殺菌消毒洗浄パック(ベビーフット)
- 薬用殺菌消臭石けん(ベビーフット)
- ブテナロック 足洗ソープ(久光製薬)
消臭靴下
- ビジネスソックス(IGRESS):メンズタイプ
- SUPER SOX(スーパーソックス) レディース フットカバー(okamoto):レディースタイプ
- 消臭スクールソックス 子供靴下(アプローズ):キッズタイプ
個人輸入で購入できる多汗症治療薬
| 商品名 | パースピレックスローション |
|---|---|
| 画像 |  |
| 有効成分 | 塩化アルミニウム・乳酸アルミニウム・エタノールほか |
| 価格 | 1本あたり2990円~ |
| メーカー・ブランド | RiemannAS |
| URL | パースピレックスローションの購入はこちら |
足の臭いに関するよくある質問

- Q足の臭いが気になる場合は何科を受診したらよいですか?
- A
まず受診するのが適しているのは「皮膚科」です。
皮膚科では、足の臭いの原因となる皮膚疾患の有無を確認することができます。
具体的には、水虫、あるいは足の多汗症などが関係していないかを調べてくれます。
これらの疾患では、足の皮膚や爪の異常が起こり、特有の臭いを発することがあります。
皮膚科医は、視診や検査で原因の皮膚疾患を診断し、適切な治療を行ってくれます。
臭いの程度やタイプ、痒みや皮膚症状の有無など、できる限り詳しく主治医に伝えることで、的確な診断と治療を受けることができます。
皮膚疾患が見つからない場合は、糖尿病や肝臓疾患などの全身疾患が関係している可能性もあります。その場合、皮膚科医から他科受診を勧められることがあるでしょう。
- Q足の臭いはつま先とかかとのどちらの方が強いですか?
- A
足の臭いについては、臭いが強い部分はつま先の方が多いと言えます。
その理由は以下の通りです。
・つま先は通気性が悪いため、湿気や熱がこもりやすい
・靴の中ではつま先が最も圧迫を受けている
・爪の間や指の間に汚れがたまりやすい
このように、つま先は汗や皮脂、垢がたまりやすく、密閉された環境になりがちです。そのためカビや雑菌が繁殖しやすく、臭いの元となる物質が多く生成されます。
- Q夏と冬だとどちらが足の臭いが目立ちますか?
- A
夏と冬では、足の臭いが目立ちやすいのは冬の方です。
夏は暑さや湿度が高いため、汗をかきやすくなります。しかし、サンダルなど通気性の良い履き物を選ぶことで、ある程度の対策ができます。
一方、冬は部屋の暖房で乾燥することが多く、通気性の悪い靴下やブーツを履く機会が増えます。閉鎖的な環境で足が蒸れ、雑菌が増殖しやすくなります。
加えて、冬は体臭を感じにくくなるため、臭いに対する自覚症状が低下しがちです。その結果、対策が後回しになり、臭いが強くなる場合があります。
したがって、足の臭いが最も気になるのは冬場と言えます。冬こそ通気性に注意し、消臭ケアを心がける必要があります。冬場の脱臭対策を徹底することで、快適に過ごせるでしょう。
- Q家の中では靴下は履かない方が良いのですか?
- A
家の中では基本的に、靴下を履かない方が足の臭いは発生しにくくなります。
理由は、靴下の中が閉鎖的な環境となり、汗や湿気、菌がたまりやすいからです。素足に比べれば通気性が劣ります。
ただし、外出から帰ってきた足の状態で家中を歩き回ると、菌が床やカーペットなどに付着してしまいます。
対策としては、
・帰宅時にはまず足を洗う
・スリッパなどを使用する場合は定期的に洗浄する
ことが大切です。
靴下を履かない分、空気に触れる機会が増え、乾燥しやすくなります。通気性を高める意味でも、基本は素足がおすすめです。付着した菌をこまめに洗い流す習慣をつけましょう。
まとめ
足の臭いの主な原因は、雑菌が作る「イソ吉草酸」です。
この物質は蒸れた靴下のようなにおいが特徴で、汗や皮脂、垢などを分解することで発生します。
足が臭い人に共通するのは、汗をかきやすいこと、靴内が蒸れやすいこと、汚れがたまりやすいことなどの特徴があるといえます。
そこでおすすめなのが、足や靴の清潔を保つこと、通気性を高めること、消臭対策を行うことです。
具体的には、足用石けんで洗浄し、爪を切って清潔に保つこと。通気性の高い靴下や日光消臭、靴インソールの使用などです。汗や皮脂、雑菌を減らし、蒸れにくい環境をつくることが大切です。
裸足にする時間を増やしたり、足浴で汚れを落としたり、消臭スプレーを吹きかけたりと、対策次第で臭いは軽減できます。
悩みの種だった足の臭いを改善したい方は、まず原因を理解し、清潔な足と通気性の良い環境づくりを心がけてみてください。キレイな足を保つ習慣が、快適な毎日を過ごすことにつながります。
出典
MSDマニュアル家庭版(みずむし)
MSDマニュアルプロフェッショナル版(みずむし)
環境省(悪臭防止法)
健栄製薬